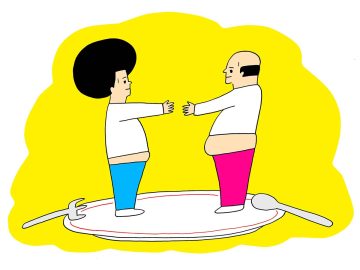手打ちへのこだわりが光る美しい「手打中華蕎麦」を実食!

現在、『かめ囲』が提供するのは、「手打中華蕎麦」(醤油・塩)、「油そば」(こってり鶏油・こっさり煮干)の計4種類の麺メニューと、その特製バージョン。初訪問ということもあり、「手打中華蕎麦」の「醤油」と「塩」を連食することにしました。

注文が入ると、その都度、提供する人数分の麺を生地から打ち始める。何と言っても、これが『かめ囲』最大の特徴です。
「当店の自家製麺は、“折り畳み、踏み、鍛える”という工程を何度も繰り返して作ります。これに、一般的な手打ちよりも多くの労力を割くので、出来上がりの麺の生地の層が数百(約200~500)にもなります」と亀井氏。
私が訪れた時も、亀井店主は四六時中、ひたすら麺打ちに取り組んでいる状態。あまりのハードワークぶりに「倒れちゃうんじゃないか!?」と心配になってしまうほど。

生地の層の厚みは、麺のクオリティを決定付ける要素のひとつである、弾力・コシの強さに直結します。ちなみにハンドメイドの極致のような極太自家製麺は、うどん粉『麺祭』を主役に、中力粉、薄力粉など、数種類の小麦粉をブレンドしたもの。
「オーダーが入ってから、提供する人数分の麺だけをその都度打ち始めるので、時間はそれなりにかかってしまいます。ただ、お客様に少しお待ちいただいてでも、打ち立て麺の魅力を味わってほしいです」と亀井氏は言います。

そうして完成した「手打中華蕎麦」は、「醤油」「塩」ともに、提供時のビジュアルを見ただけで、即座に麺のクオリティが超絶的に高いことが確信できる、渾身の仕上がり。というわけで、いざ実食です。
素材の味を活かした絶品の「手打中華蕎麦(塩)」

最初にいただいた一杯は、「手打中華蕎麦(塩)」。麺を数本箸で摘みズズッとすすり上げれば、歯を押し返すようなモッチリとした麺肌の触感が快楽中枢を心地良く刺激。噛みしめたときに麺の断面から放たれる小麦の芳香も、鼻腔を優しく癒します。

この麺に合わせるスープは、神奈川県産「湘南どり」、鹿児島県産「黒さつま鶏」、鴨などの鳥系素材をメインに、絶妙なバランス感覚で魚介素材を合わせたもの。「塩」と「醤油」に同じスープが使われているそうです。
亀井氏がとにかく常に強く意識しているのは、「お客さんの口内で、質の良いうま味をできるだけ長時間にわたって持続させること」。それを実現するため、タレについては、「塩」と「醤油」とで、異なるうま味を有する素材を使い分けているそう。結果、「塩」は素材自体のうま味を、「醤油」は香りと余韻をそれぞれフィーチャーしたものとなっています。

そんなスープと自家製麺との相性は、改めて言及するまでもなく極上のひと言。連食した「手打中華蕎麦(醤油)」もまた、醤油の香りと味が身体に染み渡る至極の一杯であり、箸とレンゲを駆使しながら、麺⇒スープ⇒麺⇒スープと、交互に食べ進めていくうちに、気が付けば丼は空っぽに。ごちそうさまでした。
まとめ

もともとラーメンが大好物で、食べ歩きを繰り返すなか、蒲田の名店『煮干しつけ麺 宮元』と出逢い、本気でラーメン職人を志すようになり、約6年に及ぶ『宮元』での修業を経て、満を持して独立した亀井店主。

近い将来、『宮元』と亀井氏との関係と同じく、『かめ囲』の味に魅せられた別の誰かが、同店の門を叩き研鑽し、新たな「スターの卵」となって、ラーメン界をけん引していくようになる…。名店から名店へと受け継がれていく、ラーメン職人のDNA。まだ少し先の話になるのかもしれませんが、そんなことを妄想してしまいました。
●著者プロフィール
田中一明
「フリークを超越した「超・ラーメンフリーク」として、自他ともに認める存在。ラーメンの探求をライフワークとし、新店の開拓、知られざる良店の発掘から、地元に根付いた実力店の紹介に至るまで、ラーメンの魅力を、多面的な角度から紹介。「アウトプットは、着実なインプットの土台があってこそ説得力を持つ」という信条から、年間700杯を超えるラーメンを、エリアを問わず実食。47都道府県のラーメン店を制覇し、現在は各市町村に根付く優良店を精力的に発掘中。