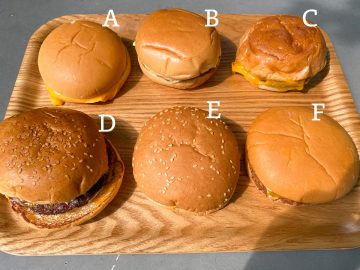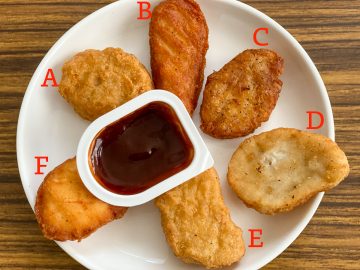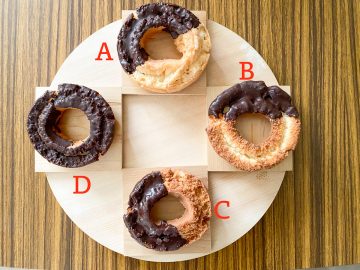「祝箸」の正しい使い方はどれ?

正月になると、誰が用意したのかどこからともなく登場し、おせちやお雑煮などをこれで食べることになる祝箸(いわいばし)。普通の箸と何が違うのでしょうか。これについて、3つのうち正解はどれ?
1:元旦の朝におせち料理に使用したら袋に戻して処分する
2:箸の先端が両口になっているので、片方はおせち料理の取り箸に使う
3:使い終わった祝箸は、神社の「お焚き上げ」に持っていく
解説
「寿」と書かれた祝箸。元旦用に用意している家庭も多いと思います。この祝箸、元旦に使ったら、洗って清め、「松の内」と呼ばれる日まで使用します(松の内は地域によって異なります)。なので、1度使ったからといってすぐに捨ててはいけません。
また、祝箸は通常の割り箸とは違い、両方の先が細くなっているのが特徴。これは、一方は神様用、一方は人用。「神人共食」と呼び、神様と食事を共にすることを意味しています。誰ですか? ひっくり返して取り箸にしてるのは。ダメですよ。
ちなみに祝箸は持ち方の作法もあります。箸先から約3cm、かなり下のほうを持ち、箸の先を汚さずに食事するのが正しいと言われていますが…これは難度が高すぎますね。なお、松の内まで使用した祝箸は、自宅で処分せずに、天に返す意味を込めて神社のお焚き上げに一緒にするのが良いとされています。
回答
1:× 2:× 3:○