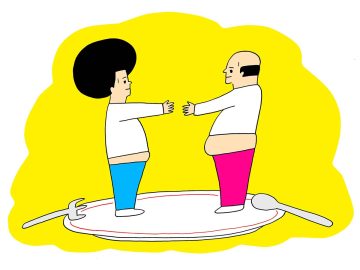老舗から新店まで、新たな味と人との出会いを求め古今東西を駆け巡るマッキー牧元さん。そんなタベアルキストが、現在までに出会ってきたさまざまな店や料理の、今は味わうことが難しい“幻の味”の記憶をひもとく。
目の前に置かれても、手が動かない。そんなすしだった。
酢飯にしなだれた白い肢体は、ほのかな飴色や薄香色の光をはらみ、色気を滲ます。銀白色の皮目が、波しぶきをきらめかせながら、つうっと流れていく。
息を呑む。いままでにこんなにも美しい鯵(アジ)には出会ったことがない。
朱色のつけ台に映えて、凛と佇んでいる。にぎりが置かれている辺りだけ、無雑な大気に包まれていて、手が出せない。
「食べなくては」。自分を律し、ゆっくりと手を伸ばして口に運んだ。
これが鯵か。いままで食べてきたのは鯵とは違う。
舌の上で脂が溶け出し、あふれていく。舌にやさしく寄り添い、緩やかに身を崩していく。
驚くほどの脂がのっているが、まったく嫌味がない。お行儀よく、舌の上を軽やかに流れ、喉に落ちていく。
残るは、ほんのりとした甘みと淡い香りで、脂の痕跡は、微塵も残さない。
五島灘の瀬に根付いた、いわゆる黄鯵の一本釣りである。今朝捕れたものを、軽く塩をし、生酢に十分ほど漬けて昼にいただく。長崎万屋町「とら寿し」の贅沢であった。
このアジの握りは、遠藤周作に愛され、山口瞳は、鯵を食べるためだけに東京から夜行列車で出かけた。
時期は八月上旬だったが、九月、七月、五月、四月の鯵も、それぞれ微妙に違った脂の乗りで、素晴らしかった。
高貴でふくよかな味。これが大衆魚なら、ふぐもシマアジも、鯛もクエも大衆魚。そんな陳腐な肩書きで呼ぶ魚ではないことを知った。
長崎万屋町「とら寿し」は、2008年2月29日に、惜しまれつつ店を閉じた。
6人入れば一杯となる小体な店には、全国から客が訪れた。だが決して高くない。お任せで握りを全部食べて5千円ほどである。
ハンサムでバリトンボイスが魅力的なご主人と奥様の二人で切り盛られていた。
今でこそ全国に、足を運びたい寿司屋ができたが、当時は東京以外に丁寧な仕事を施した寿司は皆無と言っていいほど少なかった時代である。
何しろじげもん(地場もの)だけしか握らない。だからマグロが年中ない。唯一春先に本マグロが五島の定置網に入った時期だけである。
しかも海が時化ると店を閉める。だから僕は朝、福岡から電話して、やっているかを確認してから出かけた。
淡い味付けで煮た、なめらかで溶けるような大村湾の穴子。濃密さと爽快という二律背反を秘めたウニ。清らかな体に、品のある甘みを含んだキス。銀皮が輝き、身を赤から橙色に染めて、艶やかに酢飯にしなだれる、五島の鯖は、心を惑わす爽やかな香りがあった。
中でも忘れられないのが、太刀魚の昆布締めである。1時間半ほど昆布で締めたという太刀魚は、ふっくらと分厚く、歯を入れると上品な甘みが流れ出て、もうどうにも色っぽい。そこへ酢のきいた酢飯が抱き合い、舌の上で舞う。
春先の一時だけの逸品である。
命の目覚めを切り取った切なさが、春という気分と合わさって、この世に生かされている感謝の気持ちがせり上がってくる。そんな寿司だった。
あんな寿司は、もうどこでも食べることができない。
イラスト◎死後くん
●著者プロフィール

マッキー牧元
タベアルキスト。『味の手帖』編集主幹。食と作り手への愛が溢れた文章と肉1kgをたいらげる喰いっぷりにファン多数。立ち食い蕎麦からフレンチ、割烹まで、守備範囲は広い。近頃は本誌『食楽』誌上で名料理人ぶりも披露している。