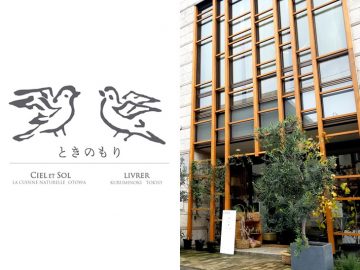シングルオリジンの日本茶でおいしいお茶のある暮らしを提案

――『煎茶堂東京』はオープン7周年を迎えましたね。
古川さん:当店は男性2人(現・代表取締役の青栁智士さんと取締役の谷本幹人さん)が立ち上げたデザインユニット『LUCY ALTER DESIGN』が母体で、2017年1月に三軒茶屋で世界初のハンドドリップの日本茶カフェ「東京茶寮」、同じ年の11月に物販専門の『煎茶堂東京』をオープンしました。
――デザイナーの方たちが、なぜ日本茶専門店を手掛けることになったのですか?
古川さん:もともと青柳と谷本の「日本人ってペットボトルのお茶は飲むけど、実はあまり日本茶を飲まないよね」という雑談から始まったそうです。自分たちも職場でペットボトルのお茶を飲むことが多いものの、お茶を淹れることがないのはなぜか……というように、話が展開していったんですね。

古川さん:茶道までいくとちょっと敷居が高く、ペットボトルと茶道の中間でカジュアルに楽しめるもの……というところから急須に着目したものの、ワレモノの急須は扱いにくい。そこで「じゃあ割れない急須を作ろうか」という流れで、まずはオリジナルの割れない「透明急須」が生まれました。
――プロダクトから入ったというところがデザイナーの方たちらしい。
古川さん:青柳と谷本がデザインした「透明急須」は石川県で作られていて、一見透明でガラス製に見えますが、樹脂で出来ているので割れません。無駄のないすっきりとしたフォルムで、海外の方のお土産にも人気がありますね。

――急須を作ったので、お茶も扱うことに?
古川さん:お茶屋問屋と繋がりがあり、そこから話が進み、お茶農家さんもご紹介いただいています。お茶屋さんには火入れからパッキングまで一貫してご対応いただき、最終的に谷本が味を確認して仕入れが決まるという流れですね。『煎茶堂東京』では、日本全国から厳選した単一農園・単一品種の茶葉、いわゆる「シングルオリジン」を中心に取り扱っています。
――シングルに特化しているお店は珍しいですね。
古川さん:そうですね。お茶は嗜好品の一部ですし、シングルのコーヒーはあるけれどお茶にはない。だったらシングルを集めてみようということになったんです。日本のお茶はブレンドされているものが多いのですが、それを知らない方が結構多くてびっくりされます。
――確かに、お茶屋さんで「これはシングルですか?」とは聞かないですよね。
古川さん:逆に、今まで飲んでいたお茶ってシングルじゃなかったんだと驚かれます(笑)。
日本茶のイメージを覆す“茶筒”のデザインとカラーの秘密

――店頭には何種類くらいのお茶があるのでしょうか?
古川さん:今、弊社で扱っている
シングルオリジンの煎茶は現在65品種、そこから約20品種ほどに絞って並べています。それを毎月2~3品種入れ変えているという感じですね。オリジナルの茶筒はイタリアのペンキ職人さんが使っている缶からヒントを得たデザインで、スタッキングができるよう上蓋がなく、かなり密閉度が高いつくりになっています。透明急須の上にジャストサイズでのる省スペース設計で、日本の台所事情をおさえているところも特徴です。
――急須も茶筒も、出しっぱなしにしていても映えますよね。
古川さん:それも考慮してデザインされています。茶筒のパッケージには、キャッチコピーや品種名、生産地、標高、焙煎温度などの情報が入っていて、その情報を数値化して独自の色に当て込み、巻紙の色を作っています。なので、色にもすべて意味があり、このカラーバリエーションが生まれています。
![斬新なカラーリングのお茶缶と、さまざまな作家の茶道具も取り扱っています[食楽web]](https://cdn.asagei.com/syokuraku/uploads/2024/11/20241117-sencyado16.jpg)
古川さん:茶葉も作物なので、年度によって出る味の変化に対応するため、火入れの温度を変えるなど調整をします。すると、巻紙の色も変わるんですね。似ている色もありますが、実は微妙に違うんですよ。また、通し番号が付いているので、数字にこだわる記念日や結婚式の引き出物にもお使いいただいています。