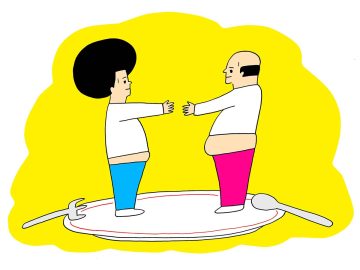日本最古の菓子店『一文字屋和輔』の「あぶり餅」

玉の輿のご利益で知られる今宮神社の参道には、「あぶり餅」を扱うお店が2軒向かい合って建っています。そのうちの一つ、『一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)』は、長保2年(1000年)創業の日本最古の菓子店。通称「一和(いちわ)」と呼ばれ、時代を超えて愛されてきました。

看板商品の「あぶり餅」は、きな粉をまぶしたお餅を竹串に刺して焼き上げ、甘い白味噌だれをかけたもの。このお餅を食べることで疫病から逃れられたという古くからの逸話が残されています。

注文を受けてから備長炭であぶられるお餅は、外はこんがり、中はふんわりとした食感。白味噌の風味とお焦げの香り、自然な甘みが広がります。11本というと多そうですが、気がつけば完食してしまうほどの美味しさ。向かいにあるもう一つのあぶり餅屋『かざり屋』と味わいが少し異なるので、食べ比べを楽しむのもおすすめです。
●SHOP INFO
一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)
TEL:075-492-6852
住:京都府京都市北区紫野今宮町69番地
営:10:00〜17:00
休:水曜(1日、15日、祝日が水曜日の場合は営業、翌日休業)、12月16日~12月31日
午前中には売り切れる『神馬堂』の「やきもち」

京都最古の神社といわれる上賀茂神社(かみがもじんじゃ)。正式名称は賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)で、今から約1350年前の677年に創建されました。その参道にある明治5年(1872年)創業の『神馬堂』の「やきもち」は、午前中に売り切れてしまうほど人気があります。

「やきもち」は粒あん入りのお餅を鉄板で焼いたもの。正式名称は「葵餅」で、上賀茂神社のご神紋である二葉葵にちなんでいるそうです。創業約150年ですが、店員さんいわく「京都の老舗のなかではまだまだ若者ですよ」とのこと。親しみやすい接客や温かい雰囲気が、訪れる人々の心を和ませています。

買ったものをすぐに食べてみると、表面がこんがりとしていて香ばしい風味が広がります。もっちりと伸びの良いお餅の中には、甘さ控えめの粒あんがたっぷり。小ぶりなサイズは食べ歩きやお茶請けにぴったりです。
●SHOP INFO
神馬堂
TEL:075-781-1377
住:京都府京都市北区上賀茂御薗口町4
営:8:00~昼頃まで(売切れ次第終了)
休:水曜
素朴なプチプチ食感『粟餅所澤屋』の「粟餅」

学問の神様が祀られ、梅の名所として有名な北野天満宮。その門前に店を構える『粟餅所・澤屋』は天和2年(1682年)、江戸幕府五代将軍・徳川綱吉の時代から茶店として営業をはじめ、300年以上にわたって伝統の技と味を守り続けています。
![風情を感じる店構え [食楽web]](https://cdn.asagei.com/syokuraku/uploads/2025/01/20250120-monzenkashi09.jpg)
看板商品の「粟餅」は、穀物の粟を使ったお餅のこと。蒸したての粟と餅米を店内の臼でついた後、こしあんときな粉をまぶして提供されます。通常のお餅と比べて堅くなりやすいため出来立てにこだわっており、注文を受けてから丸めてくれます。

粟のプチプチした食感が残るやわらかいお餅と、上品なこしあんときな粉が相性ぴったり。こしあんの方は、口に入れるとスッとなくなる滑らかさ。きな粉をまぶしたものは香ばしい風味で素朴な味わいが楽しめます。出来立てをその場で味わうのが一番ですが、テイクアウトも可能なのでお土産にするのもおすすめです。
●SHOP INFO
粟餅所・澤屋
TEL:075-461-4517
住:京都府京都市上京区今小路通御前西入ル紙屋川町838-7
営:9:00〜17:00頃(売り切れ次第終了)
休:水曜・木曜、毎月26日
門前菓子で彩る京都寺社めぐり
京都の寺社巡りでは、参拝の後に門前菓子を味わうのも風情があります。店先から漂う香ばしい香り、趣のある佇まい、そして丁寧に作られる伝統の味。至福のひとときをぜひ楽しんでみてください。
(撮影・文◎安達春香)