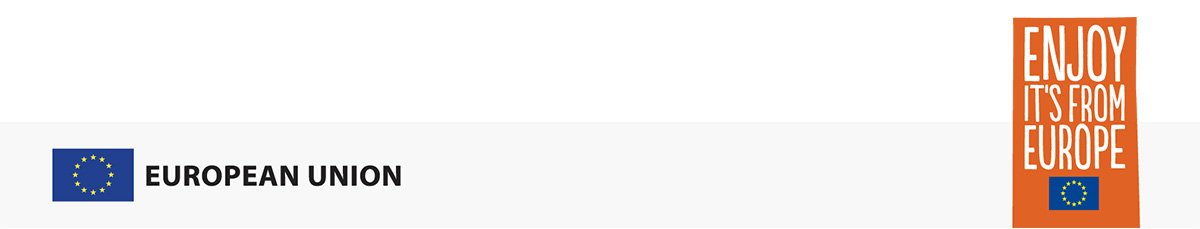ワインをはじめ、ハム・ソーセージなどの加工品、オリーブオイルなど、日本でもすっかりお馴染みのヨーロッパ食材。今やスーパーやコンビニなどでも気軽に手に入るため、日頃からお世話になっている読者の皆さんも多いのではないでしょうか。そんなヨーロッパの食材の魅力を探るべく、3月7日~10日に東京ビッグサイトで開催されたアジア最大級の見本市「FOODEX(フーデックス) JAPAN 2024」におじゃましました。
ビッグサイトに到着すると、すでに入場口は人で溢れている状態。今年の「食」トレンドや最新の食材などの情報を得たり、取り引きしたりするために、多くの食関係者が詰めかけているようです。国内外のさまざまなパビリオンを尻目に、海外ゾーンにあるEU(ヨーロッパ連合)のパビリオンへ直行します。パンフレットを見ると「ヨーロッパ食材+日本食材:パーフェクトマッチ」というテーマが。はてさて、どんなテーマなのか気になるところです。
EU27カ国の厳選食材に出会える「EUパビリオン」

肉を焼く香ばしい香りや、試飲用のワインが並ぶ姿などに後ろ髪を引かれつつ、海外ゾーンの中央を目指していると欧州旗のロゴが目に飛び込んできました。お目当てのEUパビリオンに到着です。周りには、スペインやフランス、イタリアなど国ごとのパビリオンもあり、中には行列ができている所も。今回のEUパビリオンでは、27もの加盟国の食材が出展されているとのこと。まだ知らない食材に出会えたるかも、と新たな発見に期待しつつ中へ。

EUパビリオン内は、日本向けの食材として重視しているジャンルごとに「ワイン・ビール・スピリッツ」のアルコール類、ハム、ソーセージなどの「食肉・加工肉」、「オリーブオイル」、チーズなどの「乳製品」、ジャムなどの「果物、野菜、蜂蜜」、チョコレートをはじめとする「その他農産物加工品」といったブースに分かれていて、すべて試食・試飲が可能。またステージが設置され、そこでヨーロッパの食材に関する各種プレゼンや、ヨーロッパ食材を使ったシェフによる調理実演も行われるそう。どれも面白そうで興味津々です。

ひと通りブースを回っていると、気になるロゴが目につきました。どうやら品質基準をはじめとしたロゴのようです。日本でもこうした品質基準は一般的になってきましたが、EUにもあるんですね。どんな基準が設けられているのか気になった筆者。さっそくEUパビリオンの方に話を伺うことに。

徹底した品質管理とEU食材ならでは付加価値が「違い」を生む

対応していただいたのは、EU通商部のセルジオ・ゴンザレスさんとイザベラ・デストベレアさん。
――今回のEUパビリオンはすごく力が入っているように見えます
イザベラさん:2018年から「ヨーロッパ食材と日本食材のマッチング」をテーマに出展を続けています。日本への輸出量は世界5位。コロナ禍で一時的な伸び悩みがあったものの、年々順調に輸出量、輸出額ともに伸びていて、今後も重要なマーケットだと捉えています。そんな中、重視しているのがEUならではの厳格な品質管理です。

――品質管理は日本の消費者も大いに興味がある点だと思います。具体的に教えて下さい
セルジオさん:まずベースにあるのが衛生面。輸出品に関しては、SPSという認証制度を設け、世界でも最も厳しいレベルでのチェックを行っています。またEUでは、持続的な経済社会に向けた包括的な「欧州グリーンディール」という構想を2020年に立ち上げたのですが、これに基づき、「Farm to Fork」(農場から食卓まで)という戦略が立てられました。次の世代の人々への責任として、気候変動や二酸化炭素排出の削減など、持続可能な農業を構築するためのさまざまな対策を行っています。農産物などの生産から、加工、さらに輸出を経て消費者の食卓に届くまで、あらゆる面で食材のクオリティを担保しているのです。こうしたEU食材の付加価値は、世界中の多くの国々で支持されています。

――なるほど。「原産地呼称保護」や「地理的呼称保護」、「EUオーガニックロゴ」などは、EUの厳格な政策や管理のもとでつくられたという、いわば“お墨付き”というワケですね。最後に今回の出展を通して、読者へメッセージをお願いできますでしょうか?
イザベラさん:安全や伝統、美味しさなどはもちろん、オーガニックやエシカル消費といった面でも、EUの食材は、皆さんの期待に応えられるクオリティを持っています。そしてこれらが求めやすい価格で提供されているのです。EUの食材には皆さんが期待するすべてが詰まっていると思います。
セルジオさん:農薬・化学肥料の使用もかなり制限されていますし、バクテリアなどの微生物基準も厳格です。また、アニマルウェルフェア(動物福祉)にも配慮しているなど、EUの食材は安全、環境、品質などあらゆる面で優れていることをぜひ知っていただいた上で、その魅力を楽しんでいただければと思います。

「美味しさ」への追求はもちろん、さまざまな面で厳格な基準を設け、それをクリアした食材だけが日本に入っているという、その徹底ぶりに「ここまでやるか」と舌を巻いた筆者。生産者をはじめ、食に関わる人々の大いなる努力があって日本へ届けられているのだな、と思いつつEUの食材を改めて試食・試飲したところ、その旨さも格別に感じられました。先程、紹介した「欧州保証品質ラベル」はいわば、品質と信頼の証。食品パッケージやラベルなどに記載されているで、スーパーやデパートでヨーロッパの食材を見かけたら、ぜひ手に取ってチェックしてみてはいかがでしょうか。
(撮影◎sono)