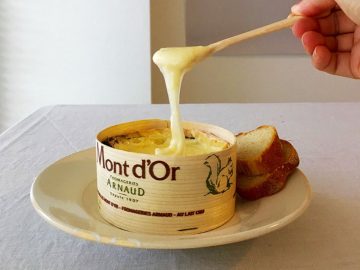刺身、卵かけご飯、冷奴、目玉焼き、大根おろし、おもち、すき焼き、煮魚、豚のしょうが焼き……日本の食卓に欠かせない調味料といえば、何と言っても醤油。日本人にとって最も身近な調味料です。
しかし、そもそも日本の醤油がどこで生まれたのか? と問われて即答できる人はそう多くないんじゃないでしょうか。ちなみに、醤油の生産地として知られる千葉県や兵庫県ではありません。
答えは、和歌山県の湯浅(ゆあさ)町です。意外ですよね。ちなみに、醤油メーカーとして有名なヤマサ醤油やヒゲタ醤油なども、ルーツをたどると湯浅の醤油に行き着きます。
はじまりの町・湯浅町へ

和歌山県中部の西岸に位置する湯浅町は、紀伊水道に面した穏やかな入江が目の前に広がる港町。
この町に醤油が生まれたのは鎌倉時代。当時、和歌山県から中国の径山寺(江蘇省・杭州)に渡った僧侶が、味噌の製法を持ち帰りました。それが今も湯浅町に伝わる金山寺味噌です。そして金山寺味噌づくりの過程で出た上澄み液。これこそが醤油のオリジンなのです。
こうして古くから醤油や金山寺味噌の醸造で栄えた湯浅町には、江戸期〜明治初期の最盛期には、100軒近くの醸造所が軒を連ねていました。令和の今も、かつて醤油醸造で隆盛を極めた時代の面影が色濃く残っており、町家や白壁の土蔵が建ち並んでいます。
その醤油の“最初の一滴”が生まれた湯浅町で、いまも天保時代から変わらぬ製法で唯一無二の醤油を造り続ける老舗醸造所が、『角長(かどちょう)』です。
醸造の町で出合った唯一無二の醤油

角長の創業は天保12(1841)年。蔵に一歩足を踏み入れると、例えようもないほど芳醇な醤油の香りが一気に鼻腔をくすぐりました。
出迎えてくれた角長の七代目・加納恒儀さんは、江戸時代からタイムスリップしてきたような男ぶりの良い職人。年季の入った前掛けに、魂が宿っているようです。

「うちの醤油は、天保時代からの伝統製法にこだわり、一から十まですべて手造り。もろみの仕込みから熟成、火入れ、最後の瓶詰めに至るまで、全部人の手でやっています」と加納さん。
醤油の原料は、大豆、小麦、塩水、麹菌。角長では大豆と小麦に麹を混ぜて寝かせた後、仕込み桶で1年半〜3年ほどかけて醸し、もろみを造ります。

醸造蔵の中に34あるという仕込み桶は最大で深さ2mほど。もろみは年代別に管理されており、静かに熟成の時を待っています。

「醸造蔵は天保時代の創業当時のもの。だから柱や梁、天井など至るところに“蔵つき酵母”が付着してるでしょ。これがもろみの酵母菌に宿ることで、初めておいしい醤油ができるんです」
こうして人の手で造られる角長のもろみは、一方で天候や気温、湿度に左右されやすいため、細心の注意を払って管理する必要があります。
「もろみも蔵つき酵母のバランスもその時々で微妙に変わる。つまり、同じ醤油は二度とできんということです」と加納さん。

こうしてじっくり時間をかけて醸し、もろみの味・香り・色合いが整ったタイミングで“圧搾”の作業に移行。麻袋にもろみを詰め、圧力をかけてじわじわと生醤油を搾り出していきます。

生醤油をほんの少しなめさせてもらったところ、非常に香り高く、奥深い余韻と旨みに満ちた、実に力強い味わいでした。
この生醤油は、半日間かけてじっくり和釜で炊き上げていきます。えぐみが出ないよう、沸騰させないギリギリの温度を保つ必要があります。もちろん、角長ではこの作業も人の手で行っています。

火入れに使う燃料はアカマツの木。加納さんいわく「火力が強く、一定の温度が維持しやすくて醤油の旨味をしっかり引き出してくれる」とのこと。
2025年現在、昔ながらの製法で造られる醤油のラインナップは次の通り。スタンダードな火入れを施した「湯浅手づくり醤油」、鎌倉・室町時代の醤油を再現したという圧搾も加熱もしない生醤油「濁り醤(にごりびしお)」、もろみ3年熟成の「匠」。
いずれも保存料などの添加物は一切なし。開封後は冷蔵保存が必須です。

東京に帰って、角長の醤油といつも使っている醤油を白身魚の刺身につけて食べ比べてみましたが、雲泥の差で角長の圧勝。試しにご飯にほんの少し垂らして食べてみたら、もうそれだけで大満足でした。
まとめ

今や醤油は世界中で愛されるポピュラーな存在になっていますが、その原型が生まれた和歌山の湯浅町には、まさに世界最高峰の逸品がありました。
ちなみに、角長本店の醸造蔵の隣には資料館もあり、湯浅の醤油づくりの歴史が学べるようになっています。和歌山を訪れることがあれば、ぜひ湯浅町に立ち寄って、江戸から変わらぬ本物の醤油を味わってみてください。
●SHOP INFO
角長 本店
住:和歌山県有田郡湯浅町湯浅7
TEL:0737-62-2035
営:9:00〜17:00
休:無休